ひとなみについて
この団体は、葬祭カウンセラーを認定しているそうだよ
でも、葬祭カウンセラーの認定は2024年春からで、もともとは宗教者と一般市民が平らな目線で車座で語りあう「ひとなみ座談会」をやっていた団体のようだわ
は~い、主宰のオケイこと勝桂子(すぐれ・けいこ)です。
2010年10月に、さまざまな宗派の知人僧侶にお声がけをして「散骨について」語らっていただいたのがきっかけで、定例化していきました。
常連の宗教者の多くが「自死自殺に向き合う僧侶の会」に所属されていたことから、〝生きづらさと向きあう任意団体〟として活動してきました。
フムフム。座談会は東京のみならず、大阪や九州、信州など全国各地で行われていたようであるな
はい、わたしが2011年の10月に『いいお坊さん ひどいお坊さん』を上梓して以来、全国各地の僧侶研修にお呼びいただくようになったので、それぞれの研修の際に事務局のお坊さまの協力をいただいて開催したり、知人僧侶のお招きで開催できたりと、自然と活動範囲がひろがりました。
して、葬祭カウンセラーなるものをひろめることとなった次第は?
10年間にわたってさまざまな宗派の講演で〝お寺を看取りステーションに〟とうたってきたんです。
ところが、10年経っても、親族を頼れない檀信徒の看取りに積極的に取り組むお寺は、数えるほどしか出現しませんでした。
お坊さまがたは月~金はほかの仕事をされている方も多く、土日は法事で忙しすぎるので、新しいことに着手するのは困難なのだと気づきました👉お寺へ企画を提案できる一般市民を葬祭カウンセラーとして養成して、菩提寺なり、気に入った宗教者のいらっしゃる寺社なりに、生き死にに関わるテーマの勉強会や催しが提案されるようにしなければ、地域での看取りは推進できない、と気づいたのです。
葬祭の基礎知識を身につけたどうしならば、死生観や人生観にかかわる話題を語り合うにふさわしいかもしれない
それにしても最近の人間たちは、葬祭を簡略化しすぎていると思うよ
亡き人に思いを馳せることをしなかったら、いつか自分もいなくなるという意識が持てないし、最期をイメージできなかったら、〝人生を精一杯謳歌しよう〟という気持ちにもなれっこないと思うんだ
ところが、ペットの葬儀は手厚くなっているんです! 弔う気持ちがないわけではない、と思います。
大家族ですごすことがなくなり、独居の人も増えて、人間どうしの距離感が複雑になっているために、親族なのに弔いたい気持ちが芽生えづらかったり、逆にインターネットで間接的に見知っているだけの人の死に衝撃を受けてしまったりと、従来の葬儀の形態ではなかなか腑に落とすことのできない別れが多くなっているように感じます。
たんに文明が進みすぎて、無味乾燥になってしまったわけではないのね!
それならば、われらももういちど皆さんが活力にあふれて人生を過ごすことができるよう、後押しができるかもしれないわ
名称の由来
ひとなみという名称には、人並みと人波という、ふたつの思いがあります。
「人並みの生活とは?」
「人並みの社会貢献とは?」
「人並みの葬儀とは?」
といったことを考えてゆくこと。
そのうえで、余分な競争意識を捨て去り、〝足ることを知って〟ゆくこと。
そして、
「連綿と続く人の歴史の大河(人波)の一点である」
という一体感・安堵感を感じてゆくこと。
そのような感性の大切さを、相談業務を通してお伝えしてゆければと考えております。
具体的には、宗教者・士業者・医師等の専門家など、たえず死生を見つめる立場にある人たちが、サイト上あるいは座談会等で意見交換し、また一般のかたがたとも交流してゆくなかで、人並みと人波、2つの ひとなみ をご提案をしてゆくことを目的とします。
ひとなみ 活動イメージ
任意団体ひとなみは、家族観が大きく変動するこの時代に、血縁をたよらなくても〝看取りあえる〟社会をめざして活動しています。
同じ墓に眠る人どうしが菩提寺で看取りに関する情報交換をしたり、じっさいに見舞いあい、看取りあうことで、血縁でなくても〝看取りをバトンタッチしてゆく〟ことが可能であると、確信しています。
そのためには、日ごろから人生観や死生観について語らう仲間をつくり、同じ地域のそうした仲間と手を携えてゆくことが肝要と考えます。
それを推進する人材として〝葬祭カウンセラー〟の育成・普及に尽力しています。
2025年現在、主宰は『いいお坊さん ひどいお坊さん』(ベスト新書、2011)の著者、勝桂子(すぐれ・けいこ)です。主宰者の著作等は以下をご覧ください。
Amazon著者セントラル:勝 桂子(すぐれ・けいこ)の著作紹介ページはこちら
【ひとなみの事業内容】
ひとなみでは2011年来、宗教者、医師、看護師、カウンセラー、相続を担当する士業者、葬祭業者、石材店など死生に関与する専門職と、一般市民とが対等の立場で語らうことのできる「ひとなみ座談会」や勉強会、「お坊さんと話そう」などの催しを主催してきました。
葬祭カウンセラー認定者を中心とした講座や勉強会の運営、電子書籍や動画の販売もしております。
🔶葬祭カウンセラー認定実用講座は、コエテコカレッジ内のこちらからどうぞ
![]() 経緯
経緯
2010年のサイト立ち上げ当初は、オケイが得意とするインタビューや座談会で、葬送をめぐる話題についてサイト上で発表してゆける場があれば、との思いで活動していました。
しかし、「戒名ソフト」についてのメールインタビュや、「散骨」についての座談会を行うなかで、参加したお坊さんの中から、「地域には、こうした話題について話し込めるお坊さんがなかなかいないので、座談会に呼んでもらって本当に嬉しい」など、意外な喜びの声をうかがいました。
活動をされているそれぞれの団体内では、みなさんそれぞれに、生死のありかたや貧困について語り合い、主義・思想について深める機会もお持ちだと思います。
しかし、その点と点とをつないでひとつの波にする必要がある、と感じたのです。多くの人がつながる、ひとつの波をつくる必要がある、と。
ここへきて、〝ひとつの大きな波〟という、「ひとなみ」という命名の第3の意味が浮上してきました。
たとえば、お経も真剣に聞いたことがないのに、紙幣を積んで院号のついた戒名をいただくようなことが人並みのご葬儀とは思えません。
あるいは、信心がとくにないからと、縁のうすかったご親戚の遺体を直接火葬場へ搬送し、僧侶の立会いもないまま遺骨にしながら、あとで「化けて出られると怖いから」と法要だけ欲してしまうような、根拠のない、流行まかせの、揺らいだ選択が、人並みの出来事であってはならないと思います。
なんらかの道しるべを示せる動き、語り合い深め合う人々による波、が必要なのです。
巷には、僧侶主催のイベントや、仏教関係者が運営するショップなども増えています。
しかし、立ち寄った友人・知人からは、「求めているものと違う」という声が高いです。
せっかくお坊さんが運営しているんだからと、倫理感や死生観にかかわるような人生相談をしてみたけれど、ピンとこない答えしか返ってこなかった、というのです。
なぜでしょう?
イチゲンの、背景もよくわからない人を相手にして、倫理的・哲学的な問いに対して答えるだけの思考を深める機会が少ないからなのではないでしょうか。
いっぽう、葬送専門として遺言・相続・改葬等のご相談に応じてきた私の周辺には、立派な士業者(弁護士・公認会計士・司法書士・行政書士・税理士・中小企業診断士etc.)がいらっしゃいます。
私などと較べたら、手続き的にテキパキと月に何十件もの相続業務をこなされている先生もいらっしゃいます。士業合同相談会などに顔を出せば、相談者の話も半ばで多くを察知され、見事というしかない手短さで「今後すべきこと」を指示される先生もいらっしゃいます。
しかしながら、相談者の顔色をうかがうと、何かが違う。そういう答えがほしかったのではなく、親族との人間関係をなんとかしたいだけなのでは? テレビで「もめそうなら公正証書遺言を」などと聞きかじって、「公正証書遺言が作りたいです」とおっしゃっているけれども、本当は、「もめそうであること」そのものをなんとかしたかっただけなのでは……、と思えるような場面に多々遭遇するのです。
こうした場合、士業者がもし、宗教者やメンタルケアの専門家やグリーフの専門家と縁をもっていたら、共にお話しをうかがうことで、心理面での問題をまず解決することへと導いてゆけるかもしれません。
さらには、先述の「僧侶主催のイベントや、仏教関係ショップ」で、満足のいく答えが得られなかった一般のかた(=理想の僧侶像、宗教のあるべき形についてなんらかのイメージを持たれているかた)が、死生を語れる専門家たちと交流し、相談に乗ってもらういっぽうで要望も述べることで、専門家たちがより一般のかたの考えに柔軟に対応できるようになることも、めざしたいと思っています。
お一人でも多くの宗教者・士業者・対話の専門家・医師等の参加をお待ちしています。
また、お寺や各種団体、企業に対し、「遺言」、「相続」、「葬儀とお墓の相談」、「エンディングノートのつくりかた」などのテーマで各種講演会・相談会等の企画をご提案いたします。
ひとなみとご縁のある、すなわち死生について日ごろから意見交換している、信頼できる寺院の僧侶や、葬儀社、士業者がうかがいます。
企画はパッケージ化されたものではなく、個別にご相談にうかがいます。
メールフォームや公式LINEから、まずは気軽にお声がけください。
This site participates in Amazon.co.jp associate.

 サイト内検索
サイト内検索





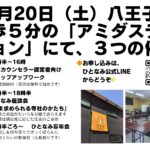

 みとり情報満載
みとり情報満載 ひとなみのYouTube
ひとなみのYouTube
