アナログでもできるお寺の貢献
今日も、コロナ禍のなかでのお寺のさまざまな尽力について、数人のお坊さまがたとメールやオンライン会議で情報交換させていただきました。
なかでも、私OkeiのFP仲間でもあり、埼玉県のお寺のご住職である高橋泰源さん(近著『必勝‼ 終活塾』双葉社)とのお話ではたくさんのヒントをいただきました。一部をご紹介いたします。

お寺は広いし掲示板があるのだから、いろいろできる!
たとえば10人程度なら「密」にならずに集えるお寺でしたら、
「●人上限で、一人置きに座っていただいての写経会をやっています。
家のなかでストレスがたまっているとお感じの方はどうぞ」
などと掲示板に貼り紙してみる。
庭の広いお寺さまであれば、午前中は園児中心、午後は小学生中心、室内は中高生中心etc.と分けて(きょうだいは別枠でなくてもよいよう、あくまでゆるく分ける)、自宅ですることのなくなった子どもたちに羽根をのばしてもらう。さらに寺子屋的なこともおこなってみるなど。
お寺にマスクが寄進されている場合などは、掲示板で「マスクお渡しできます」と掲示板に書いておき、取りにみえたかたに、自粛のなかでの困りごとや悩みがないかを聞いていく。
などなど。
たすけたい、という気持ちが先にあること
臨床宗教師の資格も取得されている泰源さん。お寺は、こういう非常時にこそ役立たなければとおっしゃいます。
「このままでは法要もどんどんキャンセルされて収入がなくなるから何かをする、ではなくて、まずはじめに〝何かの役に立ちたい〟という気持ちがあることが大事」
できることをおこなったお寺は、コロナ禍のあとも必ず頼られます。
仏教思想をただしく活かせば、逆境をチャンスに変えることができます。合掌
SNSでフォローする

関連記事

 サイト内検索
サイト内検索





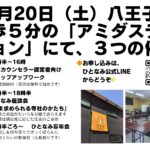

 みとり情報満載
みとり情報満載 ひとなみのYouTube
ひとなみのYouTube
